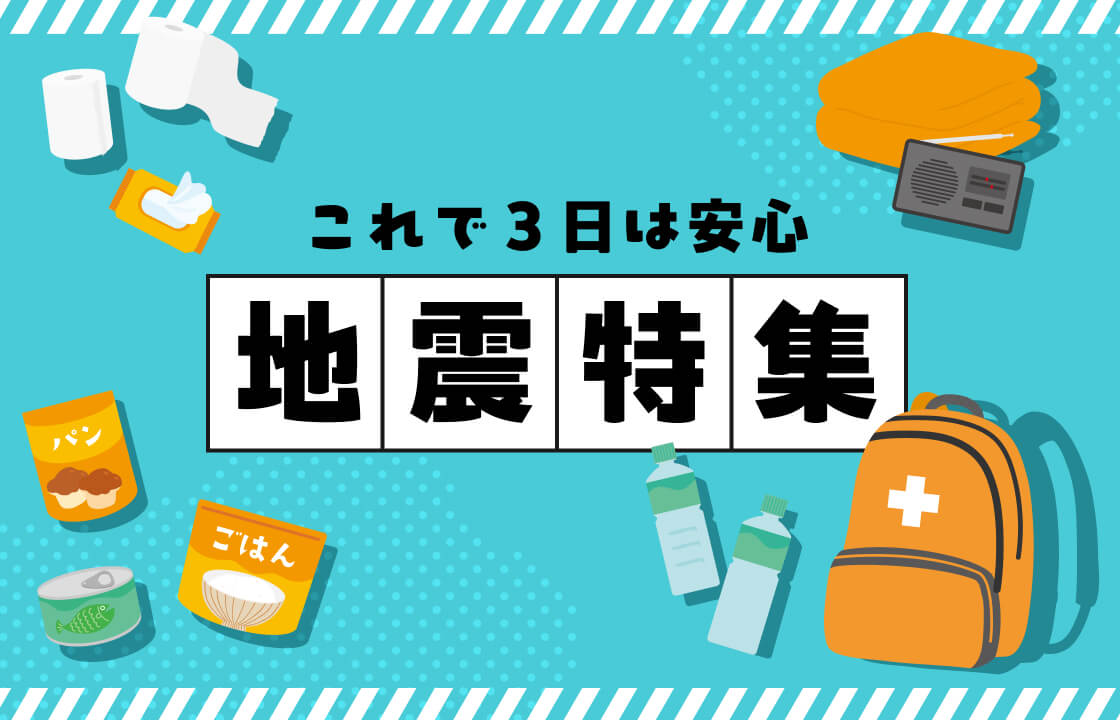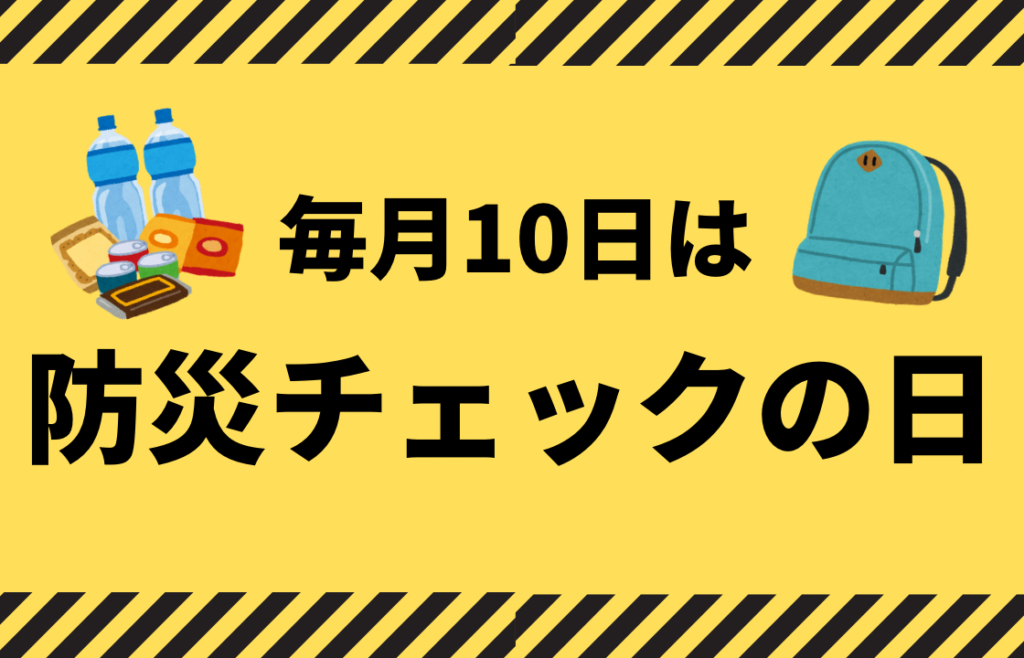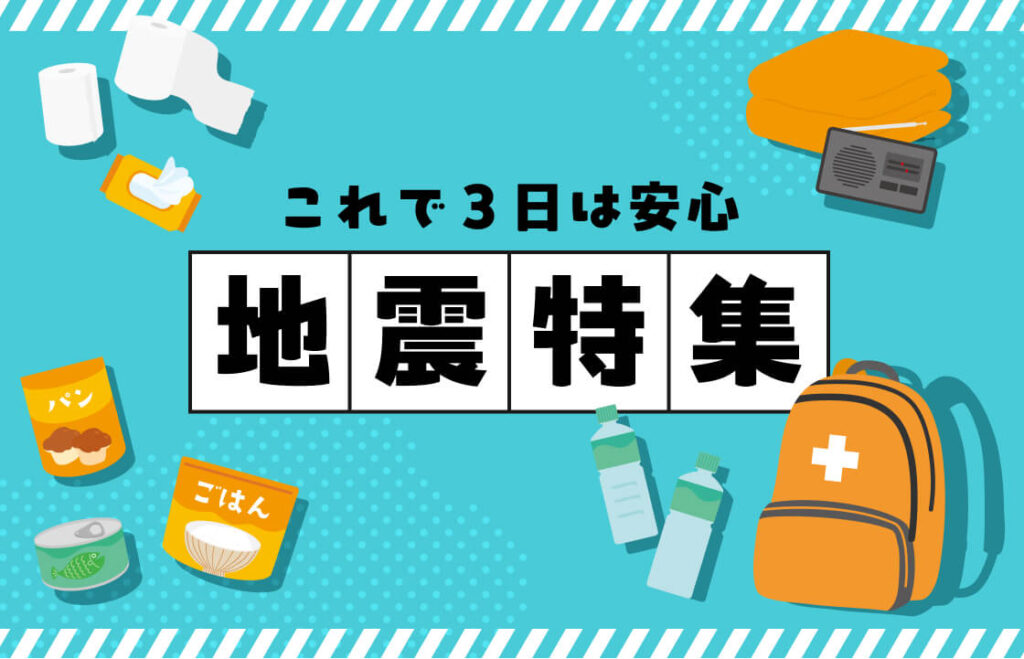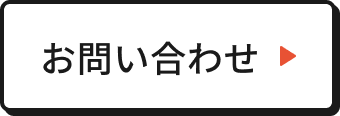
防災バッグの中身に最低限必要なものとは?必需品を徹底解説!
災害は突然やってきますが、もしもの時に必要なものを揃えていないと命を守れない可能性があります。
自分や家族に合った防災バッグを準備しておけば、万一のときにも安心です。防災バッグには最低限そろえるべき必需品があり、それらを知っておくだけでも心に余裕が生まれます。
ただし、なんでも詰め込めばよいというわけではなく、不要なものを減らす工夫も大切です。
この記事を通じて、あなたやご家族に合った防災バッグの準備を進めてみてください。
防災バッグの中身で最低限揃えておきたいものは?
最低限の必需品をそろえておけば、もしもの時も安心して行動ができます。
ここでは、防災バッグのチェックリストや適正な重さについて解説していますので、参考にしてください。
自治体や専門家が推奨する最低限の防災バッグ中身リスト
首相官邸(監修:内閣府政策統括官(防災担当)、内閣府男女共同参画局)によると、以下の備品を災害の備えとしてまとめています。
- 水
- 最低3日分の食品(ご飯、レトルト食品、ビスケット、チョコなど)
- 防災用ヘルメット・防災ずきん
- 衣類・下着
- レインウェア
- 紐なしの靴
- 懐中電灯
- 携帯ラジオ
- 予備電池・携帯充電器
- マッチ・ろうそく
- 救急用品(ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など)
- 使い捨てカイロ
- ブランケット
- 軍手
- 洗面用具
- 歯ブラシ・歯磨き粉
- タオル
- ペン・ノート
- マスク
- 手指消毒用アルコール
- 石けん・ハンドソープ
- ウェットティッシュ
- 体温計
- 貴重品(通帳、現金、運転免許証、病院の診察券など)
※上記に加えて、子供・女性・高齢者の備えも別記載あり。
たとえば、東日本大震災では、普段飲んでいる薬の名前がわからなかったときお薬手帳が役立った経験もあります。
災害時では、とっさの判断で必需品を持ち出すことが難しいため、日頃からの備えが大切です。
防災バッグの重さは何kgまで?避難に持ち出せる適正な量を知ろう
防災バッグの重さは、一般的に以下のような目安があります。
- 男性:約15㎏
- 女性:約10㎏
これは、一般的に「自分の体重の10%~15%以内」が無理なく背負える重さの基準とされているためです。たとえば、体重50㎏の人は5~7.5㎏程度の重さになります。
そのため、以下のように荷物を軽くする工夫も大切です。
- 水は小分けの500㎖ペットボトル(1Lではなく、2本に分ける)
- 非常食はコンパクトなものを選ぶ
- モバイルバッテリーやライトは軽量タイプを選ぶ
- 衣類は圧縮袋でコンパクトに
実際の避難は、長時間の徒歩移動なども想定されます。無理のない範囲で自分の体力に合わせた量を知ることが重要です。
防災バッグで本当に必要だったもの・不要だったものの違いは?
本当に必要なものとして推奨されているのは、「普段の生活の中で利用されているもの」を備えるという考え方です。
防災のために、特別なものをわざわざ用意するのではなく、日常的に使う食品などを備えることが望ましいです。災害時に、普段と大きく異なるものを使う不便さを減らし、備えを無理なく続けることにもつながります。
必要だったもの・不要だったものの中には以下のようなものがあります。
不要だったもの
- テント:避難所に入れることが多いため、持ち運びが面倒
- コンパス:実際に避難経路を確認するには不便なため、優先度が低い
- ロープ:一般的に初心者がロープを使いこなすのは難しい
- ろうそく:燃え移るリスクがあるため、災害時はLEDライトがおすすめ
必要だったもの
- 飲料水:災害時には水が止まることが多いため、脱水症を起こさないよう十分な量の確保が必要
- 非常食:調理不要で長期保存できるもの。栄養バランスも考えた食品を選ぶ。
- 懐中電灯:LEDタイプのものが長持ちし、明るさも十分です。
- 携帯トイレ:避難先にトイレがない場合に備えて、非常に役に立ちます。凝固剤が早いタイプを選ぶと安心です。
- 衛生用品:トイレットペーパーやウェットティッシュ、マスクなどの衛生用品。
一般的に「不要だったもの」とあっても、人によっては必要になることもあります。そのため、個々で判断をして、事前にしっかりと必要なものを準備することが大切です。
家族に合わせた中身のカスタマイズ方法
女性や小さな子供、高齢者の防災バッグの中身で気をつけたいことについて、以下にポイントをまとめました。
女性の防災バッグに必要なアイテム
女性特有のニーズに対応するため、生理用品や衛生管理はとても重要になります。十分な量の生理用品を備えておくことで、衛生面での不安を軽減できるからです。
女性の防災バッグに必要なものには、以下のようなものがあります。
- 水と食料
- 生理用品
- 携帯トイレ
- 常備薬
- 軽量でコンパクトな食材
- 防犯ブザー
- 衣類・下着
- 多機能ポンチョ(防寒具や雨具として使えるもの)
生理用品やおりものシートは、衛生面でも役立つ他、傷の手当などにも使えるため、持っておくと安心です。災害時には、生理用品が不足することがあるため、ナプキンやおりものシートは十分に用意しておくと良いでしょう。
小さな子供の防災バッグに必要なアイテム
- 非常食(幼児が食べやすいレトルトの離乳食やすぐに食べられるクッキーや飴など)
- 幼児用の飲料水
- おむつ(数日分)
- おしりふき
- ビニール袋
- 余分な服(とくに下着や靴下など)
- レインコート
- 幼児が必要とする薬
- お気に入りのおもちゃや絵本
- ブランケット(寒さ対策や安心感のため)
- 哺乳瓶(使い捨てタイプが便利)
- 緊急用ホイッスル(親とはぐれたときのため)
幼児の場合は、自分で持ち運べる量を調整し、軽量であることが求められます。発達段階に合わせて、定期的に内容を見直すことも大切です。

高齢者の防災バッグに必要なアイテム
高齢者の防災バッグの重さは、10㎏程度に抑えることが推奨されています。体力が低下していることが多いため、防災バッグの重さや運びやすさを重視しましょう。
高齢者の防災バッグに必要なアイテムは、以下のようなものがあげられます。
- 飲料水
- 食料(食べやすいおかゆなどの柔らかい食品。温め不要のものがおすすめ)
- 常備薬(持病がある場合は、多めの携帯を。お薬手帳も一緒に用意しておくと安心)
- 老眼鏡や補聴器
- 紙おむつや歯磨きシート
- ウェットティッシュ
- 懐中電灯
- ラジオ
- 携帯トイレ
高齢者は、生活スタイルや健康状態に合わせて、必要なアイテムをカスタマイズすることが大切です。家族構成や特別なニーズを考慮して、防災バッグの中身を調整しましょう。
防災バッグの収納場所の選び方と中身の荷造りポイント
ここでは、防災バッグの収納場所と荷造りのポイントについて解説します。ポイントを抑えて、防災バッグの中身を準備してみてください。
防災バッグの収納場所の選び方
防災バッグは、すぐに持ち出せる場所に保管することが重要です。災害の混乱の中で、すぐに持ち出せる場所に保管しておくことで、避難を迅速に行うことができるためです。
たとえば、以下のような場所がおすすめです。
- 玄関付近(避難時、必ず通りやすい場所であるため家族も把握しやすい)
- 寝室の枕元やベッドの近く(寝室が2階の場合は、避難経路の確保も考慮する)
- 分散収納(家の中の複数の場所に分散して収納しておく)
地震や火災などの突然の災害では、1秒でも早く行動することが命を守ることにつながります。また、玄関など日常的に目にする場所で保管することで、家族の防災意識も高まるでしょう。
防災バッグの中身の荷造りポイント
防災バッグに荷物を詰める際は、重いものを下に、軽いものを上にする「重心」を考慮すると良いでしょう。重心を意識することで、持ち運びやすくなったり、身体のバランスが取りやすくケガのリスクを減らしたりすることができます。
以下のポイントをおさえて、荷造りをすると良いでしょう。
- 重心
- 用途ごとに透明な袋に分けたアイテム整理
- 定期的な見直し
重心を考慮した防災バッグは、持ち運びが楽になるだけではなく、精神的な安心感にもつながるため、冷静な行動ができるようになります。
防災バッグを家族で備えるメリット
防災バッグを家族で準備しておくことは、災害が発生した時に必要な物資がそろっているという安心感につながります。緊急時になにを持ち出すか考える時間が省け、迅速な行動ができるようになるのです。
防災バッグを家族で共有するメリットは以下のような点があげられます。
- 災害発生時に迅速な対応が可能
- 防災について話し合うことで、全員が同じ認識で各自の役割や避難計画ができる
- 個々の負担の軽減(重い荷物を分担するなど役割分割ができる)
- 家族全体の防災意識を高め、もしもの時に冷静な行動ができるようになる
防災バッグを家族で共有することは、災害時の安全性を高めることにつながります。もしもの時に迅速に対応ができるよう、日頃から家族で防災について話し合いましょう。
よくある質問
- 防災バッグと備蓄品はどう違う?
-
防災バッグは、緊急時に持ち出すものであり、備蓄品は自宅での生活を長期的に支えるための準備です。
両方を準備することで、災害時の不安を軽減し、冷静な対応ができるようになります。
- 市販の防災バッグを買うだけで大丈夫?
-
市販の防災バッグを購入することは、災害に備えるための一つの手段になりますが、十分ではない場合が多くあります。家族のニーズに応じたカスタマイズが必要だったり、必要な物資の見極めが必要だからです。
たとえば、飲料水は一人あたり1日2~3L必要とされますが、家族全員の量を考慮するとかなりの分量になります。
市販の防災バッグは便利ですが、それだけでは不十分です。そのため、総合的に判断する必要があります。
- 中身を見直す頻度はどれくらい?
-
防災バッグの中身を見直す頻度は、半年に1回か遅くとも1年に1回は確認できることが理想です。
防災食品や飲料水の賞味期限、懐中電灯などの動作確認などが定期的に必要だからです。
とくに、季節の変わり目である3月と9月に中身を入れ替えると、夏は熱中症対策、冬は防寒対策ができます。
定期的な見直しを行うことで、もしもの時に役立つ防災バッグを保てます。
まとめ
防災バッグの中身を整えておけば、もしもの時に安心して行動ができます。
- 防災バッグの中身は、家族構成やライフスタイルに合わせてカスタマイズが必要
- 防災バッグの重さは、男性約15㎏・女性約10㎏が目安
- 保管場所は、玄関や寝室がおすすめ
- 荷造りのポイントは、重いものを下にし、軽いものを上に重心を意識する
災害は、いつどのようにして起こるかわかりません。そのため、もしもの時に落ち着いて行動ができるよう、日頃から防災バッグを備えておくことが重要です。
この記事を参考に、まずは身近な防災アイテムのチェックから始めてみましょう。